シングルスで勝つためには、コートの線やエリアを「知っている」から「使いこなす」段階へ進めることが欠かせません。ラインの意味やサービス有効域の境目、ネット高や支柱位置などの前提が曖昧だと、狙えるコースが無意識に狭まり、守備の初動も遅れます。本稿では、バドミントンのコートをシングルス基準で読む力を軸に、寸法の根拠と運用のコツを体系化します。判定の原則とありがちな誤解を解き、練習へ落とす手順まで一気通貫で示します。長い説明は要点で区切り、現場で即使える指標を添えます。
読み終えた瞬間から、自分の守備位置と配球の幅を1本広げられる状態を目指します。
- 線は「入るための境界」で、触れた着地は有効になります。
- シングルスの有効幅はダブルスより狭く、縦は全長を使います。
- サービスの有効域は対角で、短い線を越え、長い線を出ないことが条件です。
- ネットは中央がわずかに低く、角度の作り方に影響します。
- 守備の基準位置は「センター一歩後ろ」を起点に調整します。
バドミントンのコートをシングルスで理解|短時間で把握
まずは線の役割と距離感を確定し、判断のブレを消します。ここでのゴールは、有効幅・有効長・ネット高の三要素を一体で理解することです。数字は暗記でなく、配球と守備位置の決定に直結させます。
表:シングルスで使う主な寸法と線の意味
| 項目 | 値・位置 | 対象 | 実戦での意味 |
| コート長 | 13.40m | 全競技共通 | 縦の押し戻しで時間を奪う基準 |
| シングルス幅 | 5.18m | 内側サイドライン | 外側へ出る球はアウト判定 |
| ダブルス幅 | 6.10m | 外側サイドライン | 比較基準。練習で錯覚に注意 |
| 短いサービスライン | ネットから1.98m | 両種目 | 越えないサーブはフォルト |
| 長いサービスライン | シングルスは最奥 | シングルス | 奥まで有効。深いサーブで時間獲得 |
| ダブルス長いサービスライン | 最奥手前0.76m | ダブルス | 比較用。シングルスと混同禁止 |
| ネット高(中央) | 1.524m | 全競技 | 角度・ヘアピンの基準 |
| ネット高(ポスト) | 1.55m | 全競技 | 中央がわずかに低い前提で配球 |
注意:シングルスのサイドは内側ラインが有効域です。外側ラインは練習で使うことがあっても試合の判定には関与しません。
ミニ用語集
- 内側サイドライン:シングルスでの有効な左右の境界線
- 外側サイドライン:ダブルスの左右境界。シングルスでは無効
- 短いサービスライン:サーブが越えるべき手前の境界
- 長いサービスライン(複):サーブの奥の上限線。種目で異なる
- センターライン:サービスコートを左右に分ける境界
線は「入れるための味方」になる
着地が線に触れた球は有効で、ギリギリの狙いを可能にします。ラインを嫌って内側へ逃がすと、相手に時間を与えます。練習ではマーカーを置いて「線を使う」感覚を早期に育てます。
シングルス幅5.18mを身体感覚に落とす
端から端までをステップ数で把握し、逆を取られたときの最短復帰ルートを体に刻みます。センター寄りの守備位置を1歩下げるだけで、対角の距離が縮むことを確認します。
ネット高の微差が球質を変える
中央が低いぶん、直線的な球は中央寄りほど通しやすいです。クロスのドロップやヘアピンは、角度を作るために接点を高めに確保します。
短いサービスラインの価値
前に落とすサーブの質は、この線の越え方で決まります。ギリギリを越える低さは理想ですが、まずは浮かせない再現性を優先し、成功率を80%まで上げます。
長いサービスラインと奥狙い
シングルスは最奥まで有効です。深いロブサーブは相手の初動を遅らせます。ミスを避けるため、最初はライン手前50cmを箱として狙います。
サービスコートとレシーブの原則を定着させる

サーブとレシーブは点の起点であり、エリアの理解がそのまま失点率に直結します。ここでは対角の原則、左右の始点、足の位置の条件を整理し、フォルトを未然に防ぐ基準を明確にします。
手順ステップ:サーブ前の確認
- スコアの偶奇で立ち位置(右・左)を確定します。
- 両足はサービスコート内で静止し、ライン上を踏まないよう確認します。
- 相手の位置を一瞥し、狙いの高さとコースを決めます。
- ショートは低く速く、ロブは高く深くを徹底します。
- 打った後の初動を決め、次の球に備えます。
比較:ショートサーブとロブサーブ
- ショート:ネット直上を通す低さで、前に引き出す狙いが中心です。
- ロブ:奥を深く突き、時間を奪ってラリーの主導権を取り戻します。
Q&AミニFAQ
- Q: 足は動いても良い? A: 打球まで静止が原則です。踏み替えはフォルトの原因になります。
- Q: センターラインに触れたら? A: 着地が触れた球はインですが、サーブ時の足は踏んではいけません。
- Q: 偶数スコアのサーブ位置は? A: 右側からスタートします。
対角の起点とスコアの偶奇
偶数点は右、奇数点は左から対角へ。立ち位置を毎回声に出して確認すれば、緊張場面での取り違えを防げます。相手の重心を見て、外・内を打ち分けます。
足の位置とラケット面の向き
足はコート内で静止し、ラインに触れないこと。ラケット面は早めに作り、ショートは低い放物線、ロブは弾道の頂点を高くします。面の作り直しは情報を漏らします。
レシーブの構えと返球箱
ショートには前足を出す準備、ロブには後ろへの一歩を先に用意します。返球はセンターを起点に、相手のバック側へ少しずらすと主導権を取りやすいです。
配置と動線:シングルスの守備位置と配球設計
守備の初期位置と移動の線は、エリア理解から逆算されるべきです。ここではセンター一歩後ろを起点に、相手の選択を二択に絞るための配球設計を学び、無駄な距離を削る動線を身につけます。
有序リスト:基準位置を決める順序
- 相手の利き腕と得意コースを把握します。
- 自分の弱点側をカバーする角度で立ちます。
- 打った球に応じた戻り位置を固定化します。
- コースが外れた際の最短ルートを決めておきます。
- 前後の揺さぶりに耐えるため、重心は低く保ちます。
- 配球の狙いを声に出してから打つ癖を付けます。
- 最後に実戦速度で検証して微調整します。
ミニ統計(目安)
- センター復帰まで0.8秒以内で次球対応が安定します。
- 対角クリアの着弾誤差60cm以内で主導権が継続します。
- ネット前処理→後方移動2歩で届く位置が理想です。
ミニチェックリスト
- 返球後に視線がボールだけに固定されていないか。
- 戻りながら次のコースを決めているか。
- 逆を取られた時の避難コースを用意しているか。
- センターで止まらず、半歩前に重心を置いているか。
- 外へ振られた時もネットに背を向けないか。
基準位置の設計
相手の選択肢を二択に狭める位置取りを優先します。外に寄り過ぎると対角が空き、中央に寄り過ぎるとサイドが弱くなります。打点と球質から逆算して、戻り位置を数十cm単位で最適化します。
配球で走らせる
深い対角で後ろへ下げ、浅いクロスで前へ引く。二本のセットで距離を稼ぎ、三本目で空いた空間を突きます。線を怖がらず、触れる着地を狙いに含めます。
動線の無駄を削る
一歩目の向きをコースと一致させると、移動距離が縮みます。サイドステップだけで追わず、斜め前後の踏み出しを使います。復帰は円弧ではなく、短い直線で戻ります。
判定と勘違いを正す:ライン・ネット・サービスの境界
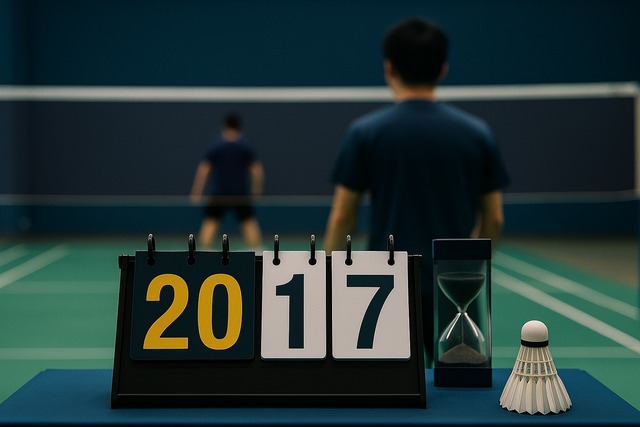
判定の原則を誤解すると、余計に安全側へ外してしまい、攻撃幅が狭まります。ここではラインの扱い、ネット周りのルールの要点、サービス時の細かな条件を整理し、迷いをゼロにします。
よくある失敗と回避策
- 線を避ける → 触れてもイン。箱の縁を狙う意識へ。
- サーブで足が動く → 静止を徹底。構え直しはボディで調整。
- ネット直後で触る → 相手の打球を妨げない距離を保つ。
ラインは敵ではありません。境界は「入れるための味方」で、ギリギリを使う勇気が配球の幅を一段広げます。
無序リスト:判定の原則
- 着地が線に触れた球はインになります。
- サーブ時、両足はコート内で静止し、ライン上を踏めません。
- ネットや支柱にラケットで過度に触れるとフォルトです。
- 相手の打球を妨げる行為はフォルトになります。
- ダブルスの長いサービスラインと混同しないこと。
ラインの扱いを攻めに転じる
狙いの箱を線の内側5〜10cmに設定し、成功率を測定します。練習ではマーカーを線上に置き、恐怖心を消していきます。成功率が上がるほど、角を攻める幅を広げます。
ネット周りの注意
面の振り過ぎは接触のリスクを高めます。ネット直上は小さな面操作で処理し、身体はネットに近づけすぎないようにします。横振りのワイパーは角度がつき過ぎるため注意します。
サービス時の細則を味方にする
踏み替えの癖は早いうちに矯正します。打球直前の微調整は上体と面で済ませ、足は動かさない。ショートの高さとロブの深さを分けて練習し、どちらも一定の再現性を持たせます。
練習ドリル:コートの線を使って精度を上げる
理解を技術に変えるには、測定可能なドリルが最短です。ここでは線と寸法を直接課題化し、成功率で管理する練習を提示します。役割を分け、短時間でも成果が出る設計にします。
ベンチマーク早見
- ショートサーブ:短い線越え50cm以内で8/10本成功
- ロブサーブ:最奥手前50cm以内で8/10本成功
- 対角クリア:線上±60cmで8/10本成功
- 前後連結(浅→深):3本連続の成功を5セット
- ネット前処理:ヘアピン対角5往復ノーミス
表:線を使う精度ドリル例
| ドリル | 狙いの線 | 成功条件 | 回数 |
| ショートサーブ箱 | 短い線直後 | 越え50cm以内 | 10本×3 |
| ロブ深さ固定 | 最奥手前 | 50cm以内 | 10本×3 |
| 対角クリア精度 | シングルスサイド | ±60cm | 10本×3 |
| 前後揺さぶり | 短い線/奥 | 3本連結 | 5セット |
| ヘアピン往復 | ネット直下 | 5往復 | 3セット |
手順ステップ:測定→修正→再測定
- 10本で現在地を測ります(成功数と誤差)。
- 修正点は1つだけ選び、意識配分を決めます。
- 同条件で10本を再度実施し、差分を確認します。
線上を怖がらない感覚づくり
マーカーを線の内側に置き、当てても良い課題から入ります。「触れても入る」を身体で理解すると、配球の幅が自然に広がります。
サービスの高さと深さの住み分け
ショートは低く速く、ロブは高く深く。弾道の違いを視覚化し、打点の高さと面の角度を別々に管理します。再現性が上がるとレシーブの予測を外しやすくなります。
前後連結で時間を奪う
浅い球で前に引き、深い球で背中を向けさせる連結は、線の理解が深いほど安全に行えます。角を攻める前に、箱の成功率を安定させます。
戦術に落とす:シングルスで線とエリアを活かす設計
最後に、理解した寸法と判定を試合の選択へ変換します。ここでは相手の位置と重心から逆算し、外と内・浅と深の二軸で戦術を組み立てます。安全域と攻めの境目を明確にし、ミスの少ない勝ち方を目指します。
比較:安全域と攻め域
- 安全域:線の内側50cmを箱にし、成功率を優先します。
- 攻め域:線上±10cmへ段階的に拡張し、ポイントを狙います。
Q&AミニFAQ(戦術)」
- Q: 角を狙うタイミングは? A: ラリーで姿勢が崩れた瞬間に限定します。
- Q: センターを使う意味は? A: 予測を外し、守備距離を縮める効果があります。
- Q: クロスとストレートの比率は? A: 6:4を基準に相手で微調整します。
ミニ統計(実戦目標)
- ラリー20本でアウト0〜2本に収めます。
- サーブのフォルト率は1ゲームで1回以内。
- 線上を使う得点はゲームあたり2点以上を目標にします。
外と内の同フォーム打ち分け
同じ前振りから外(ライン寄り)と内(センター寄り)を出し分け、相手の初動を遅らせます。読みを外すほど線上が使いやすくなります。
浅と深の連結で崩す
ネット前で落としてから深く押し返す、または深く押してから浅く落とす。前後の振幅を大きくするほど、相手の戻りが間に合いません。
ミスを設計で減らす
「角を狙う日」と「箱を固める日」を分けます。攻め域の練習は成功率60%から始め、70%を超えたら実戦投入します。設計でムラを抑えます。
まとめ
シングルスでは、コートの線とエリアを「入れるための味方」に変えることが勝ち筋になります。幅5.18mの内側ライン、短いサービスラインの越え方、最奥まで使える長いサービスライン、中央が低いネット高という前提を、配球と守備位置に直結させましょう。
練習では線上±の箱を設定し、成功率で管理します。試合では安全域と攻め域を切り替え、姿勢が崩れた瞬間だけ角を突きます。理解が精度へ、精度が主導権へとつながり、一本の違いがゲームの流れを静かに変えていきます。



